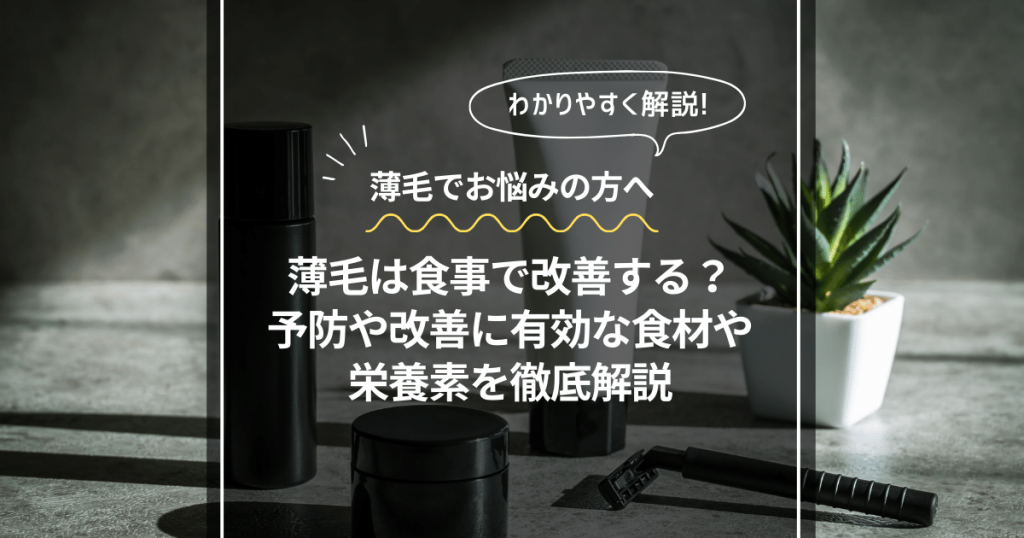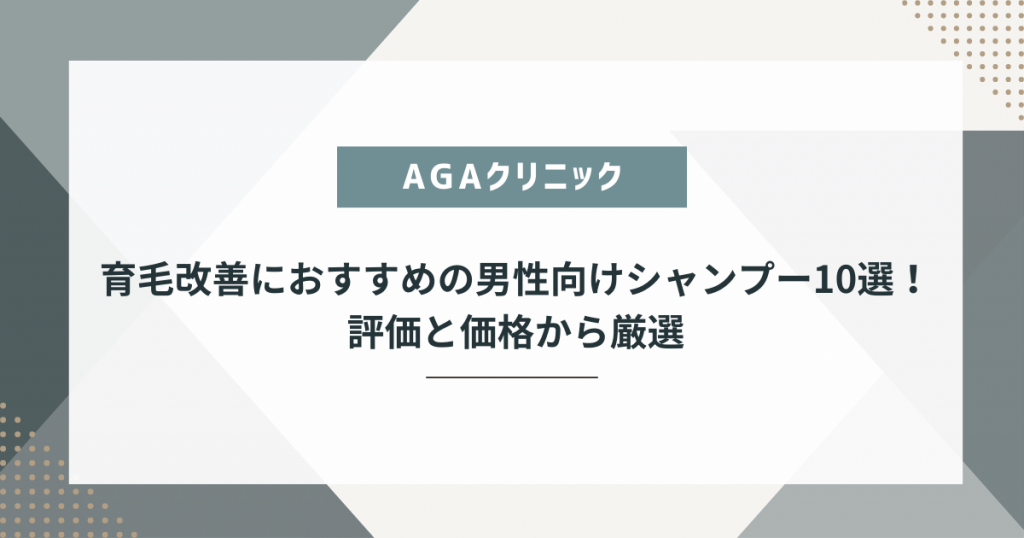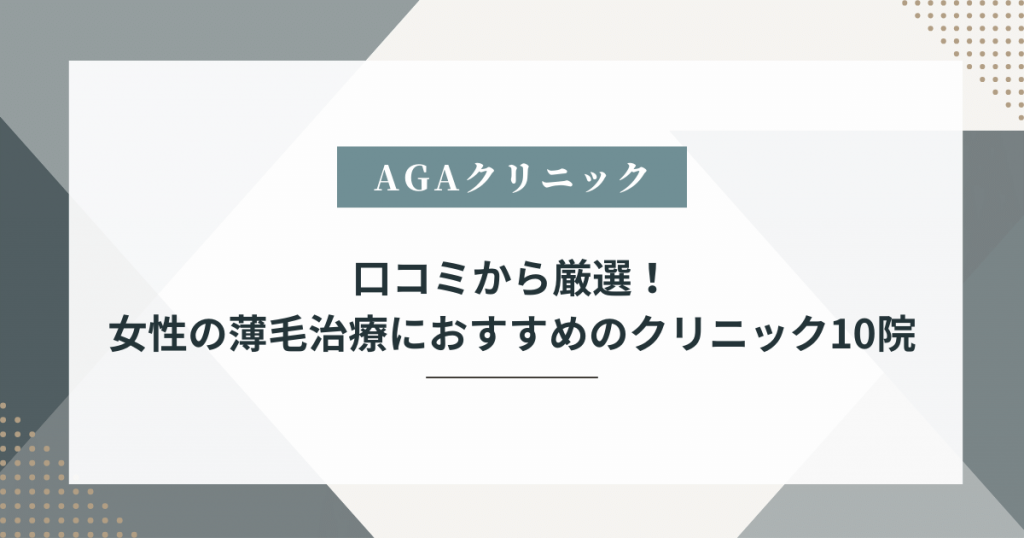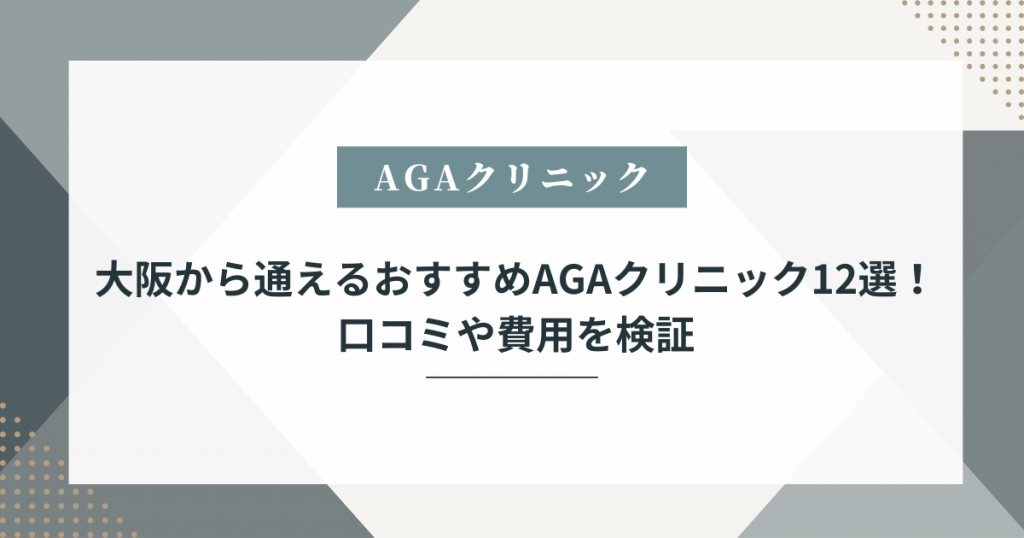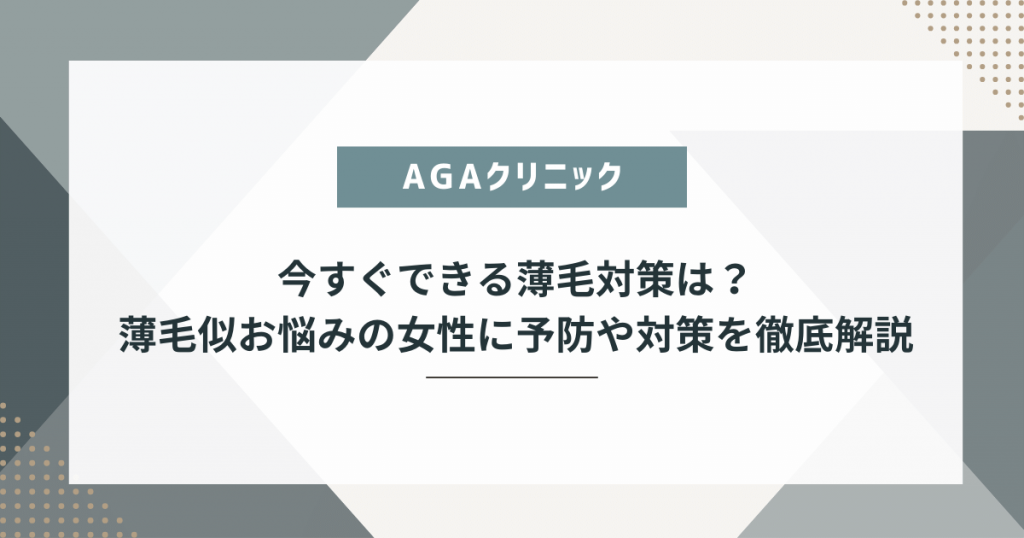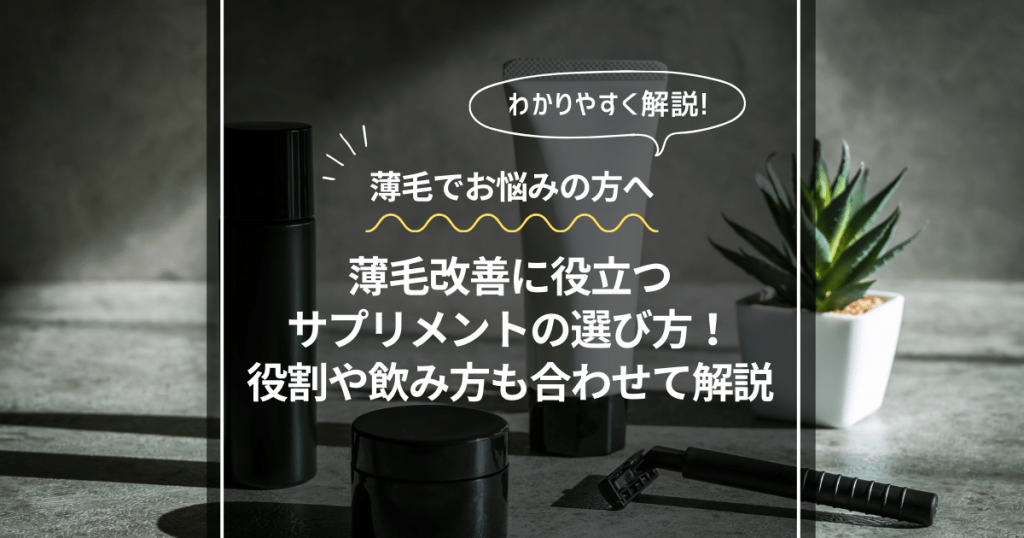
※日本皮膚科学会ガイドライン「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版」を参考にしています。
※本記事内の口コミや体験談は個人の感想であり、個人差があり、効果効能を保証するものではありません。
※本記事は2023年12月時点の情報を掲載しています。最新の情報については各クリニックの公式サイトをご参照ください。
※掲載されているクリニックは編集部による推薦です。商品、施術については自由診療であり、保険適用外になります。
薄毛改善のサプリメントは沢山売られているけど、どのサプリメントを選べばいいのか分からないと困っていませんか?サプリメントを使うときは、自分の目的に適した成分を選びましょう。ただし髪を直接増やすサプリメントは存在しないので注意が必要です。
この記事では、薄毛対策におけるサプリメントの役割や選び方、正しい飲み方などを解説しています。合わせて育毛サプリメントに関する疑問や質問にも回答しているので、薄毛対策としてサプリメントの使用を検討している方はぜひ読み進めてください。
1分でわかる!記事の内容
- サプリメントは自身の症状や目的、薄毛の原因に合わせて選ぶ
- サプリメントの役割はあくまで「育毛を補助する成分の摂取」である
- サプリメントを使用するときは、用法用量や医師の指示を守りましょう
サプリメントの選び方

サプリメントを選ぶ際は、自身の症状や目的、薄毛の原因に合った効果成分が含まれているか否かを成分表でチェックしましょう。頭皮が乾燥しているなら保湿効果の高い成分、無理なダイエットによる薄毛なら栄養素というように選ぶのがおすすめです。
しかしどの成分が自分に合うのか分からない方もおられるでしょう。この章では、サプリメントの選び方で迷っている方のために、おすすめの成分を以下のパターン別に紹介しています。
- 加齢に伴う薄毛対策
- 栄養不足による薄毛対策
- 薄毛対策のサポート
それぞれのパターンについて詳しく解説します。
加齢に伴う薄毛対策
加齢に伴う薄毛対策には、ホルモンバランスを整えるサプリメントを選びましょう。年齢と共に様々なホルモンが減少することで、体内の代謝や細胞の働きのバランスも崩れてしまいます。その結果、薄毛が発症します。
そのため年齢とともに薄毛や抜け毛が増えてきたら、ホルモンバランスを整える成分を摂取したり、生活習慣を心がけたりするのをおすすめします。
以下の表にホルモンバランスを整える成分をまとめたので、サプリメントや食事の際の参考にしてください。
| 成分(栄養素) | 役割 |
| 大豆イソフラボン | エストロゲン(女性ホルモンの1種)に似た働きをする薄毛の原因であるジヒドロテストステロン(男性ホルモンの1種)の生成を抑制する |
| ノコギリヤシエキス | 薄毛の原因であるジヒドロテストステロンの生成を抑制する |
ただし大豆イソフラボンの過剰摂取は、身体に悪影響を及ぼす可能性があるため、サプリメントを使用するときは用法用量を確認し、正しく守りましょう。
【出典:大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A|農林水産省】
栄養不足による薄毛対策
栄養不足による薄毛対策には、不足した栄養素が含まれているサプリメントを選びましょう。栄養不足は髪の健康も損ねてしまうため、薄毛に繋がります。太く、健康な髪を育てるには、十分な栄養素が必要不可欠です。
そのため無理なダイエットや乱れた食生活などで栄養不足に陥り、薄毛になってしまった方は、育毛に関わる栄養素を取り入れましょう。サプリメントを検討しているなら、以下の表に記載した栄養素が含まれている製品がおすすめです。
| 成分(栄養素) | 役割 |
| ケラチン加水分解質 | 毛髪の生成をサポートする(髪の構成物質であるケラチンを吸収しやすくしている) |
| L-リジン | ケラチンの合成を促す(体内では生成できない必須アミノ酸の1種) |
| ロイシン | |
| シスチン | ケラチンの合成を促す |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける |
| ビタミン類(特にA、B群、C、E) | 頭皮環境を整える |
| コラーゲンペプチド | 肌を潤し、弾力や柔らかさのある頭皮に導く毛細血管を発達・毛母細胞を活性化させる |
薄毛対策のサポート
薄毛対策としてサプリメントを選ぶ際は、頭皮環境の改善や血行促進を手助けする成分が含まれている製品もおすすめです。頭皮が潤うと髪の毛が痛みにくくなり、血行がよくなると栄養素が髪に届きやすくなるので、育毛に役立ちます。
そのため自分が欲しい効果を持つ成分が含まれているか成分表でチェックして、サプリメントを選びましょう。普段の食事でも積極的に取ることをおすすめします。
以下の表に薄毛改善をサポートする成分をまとめました。食事やサプリメント選びの参考にしてください。
| 成分(栄養素) | 役割 |
| カプサイシン | 血行を促進する |
| リコピン | 抗酸化作用により血管を健康に保つ血流を改善する |
| 高麗人参 | 血行を促進するサポニンが含まれている |
| 菊芋 | 胃腸を刺激し、細胞の成長に関わる「IGF-1」の分泌を促すイヌリンが含まれている |
| グルタミン酸 | 頭皮の潤いを保つ |
サプリメントの役割

育毛改善によいとされるサプリメントの役割は「育毛を補助する成分の摂取」です。育毛を促進させたり、薄毛を直接的に改善したりするような効果はありません。あくまで育毛をサポートする「健康食品」であることを、念頭に使用してください。
育毛改善で使用されるサプリメントの役割を大まかに分けると以下の3つになります。
- 育毛に必要な栄養素の補給
- ホルモンバランスを整える
- 育毛環境を整える
この章では、薄毛改善にサプリメントがよいといわれる理由をサプリメントの役割から解説していきます。
役割① 育毛に必要な栄養素の補給
サプリメントの役割で最も多いのが、栄養素の補給です。近年、摂取カロリーは足りているのに栄養不足になる「現代型栄養失調」が増えています。糖質と脂質に偏った生活やダイエット、忙しさによる食事の減少が原因です。
実際、日本における育毛に関わる栄養素の平均摂取量と摂取推奨量を以下の表にまとめてみると、30代であってもたんぱく質とビタミンE以外の栄養素が不足していることが分かります。栄養不足は薄毛の原因にもなるので、薄毛を予防・改善するなら早急な対策が必要です。
ですが1日の食事量は限られており、全ての栄養素を十分に取るのは難しいでしょう。そのため普段の食事では不足しがちな栄養素の補助として、サプリメントは有効です。
栄養素(1日あたり) | 男性 | 女性 | ||
| 摂取量平均値(30〜39歳) | 推奨量(30〜49歳) | 摂取量平均値(30〜39歳) | 推奨量(30〜49歳) | |
| たんぱく質(g) | 74.8 | 65 | 61.6 | 50 |
| ビタミンA(μgRAE) | 474 | 900 | 409 | 700 |
| ビタミンB2(mg) | 1.10 | 1.6 | 1.00 | 1.2 |
| ビタミンB6(mg) | 1.13 | 1.4 | 0.96 | 1.1 |
| 葉酸(μg) | 253 | 240 | 233 | 240 |
| ビタミンC(mg) | 66 | 100 | 65 | 100 |
| 亜鉛(mg) | 9.1 | 11 | 7.3 | 8 |
| 摂取量平均値(30〜39歳) | 目安量 | 摂取量平均値(30〜39歳) | 目安量 | |
| ビタミンE(mg) | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 5.5 |
【出典:日本人の食事摂取基準(2020年版)】
役割② ホルモンバランスを整える
薄毛改善におけるサプリメントの役割は、ホルモンバランスの調整です。加齢やストレス、生活習慣の乱れなどにより、エストロゲン(女性ホルモンの1種)が減少すると、ジヒドロテストステロン(男性ホルモンの1種)が生成・活性化するため、薄毛が発症します。
薄毛を改善するには、まず乱れたホルモンバランスを整えなければなりません。そのためジヒドロテストステロンの生成を抑制する成分や、女性ホルモンを補う成分を摂取する手段としてサプリメントがよく使われています。
役割③ 育毛環境を整える
育毛環境を整えることも、薄毛対策におけるサプリメントの役割といえます。頭皮環境や血行によい成分を食品のみで摂取し続けるのは困難です。食事の度に意識するのも大変ですし、無理に摂取しようとすると逆に食事バランスが崩れかねません。
サプリメントなら摂取に対して手間も少ないため、無理なくライフスタイルに取り入れられます。普段の食事を補う形で上手に利用し、頭皮環境を整えることで、薄毛対策をしていきましょう。
サプリメントの正しい飲み方

サプリメントは特定の成分を摂取するのに大変便利ですが、正しく飲む必要があります。
サプリメントを正しく飲むためのポイントは以下の通りです。
- ・目安量・規定量を守る
- ・水か白湯で飲む
- ・長期的に飲み続ける
- ・他の薬との飲み合わせに注意する
この章では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
目安量・規定量を守る
サプリメントには、目安量・規定量が定められています。取り過ぎの場合には、中毒症状に陥る危険性があるため、説明書の注意や目安量・規定量はしっかりと目を通しましょう。
実際、ビタミンDのサプリメントの過剰摂取で腎臓の働きが悪化したケースもあります。
そのためサプリメントを使用するときは、自己判断で摂取量を増やさず、説明書に書かれた目安量・規定量を必ず守ってください。
また過剰摂取による一部の症状を以下の表にまとめたので、不安な方は1度確認してみましょう。
| 成分 | 過剰摂取による症状 |
| ビタミンA | 吐き気、頭痛、めまい、目のかすみ、肝臓の異常、骨や皮膚の変化など |
| ビタミンD | 腎臓や筋肉へのカルシウム沈着、軟組織の石灰化、嘔吐、食欲不振、体重減少など |
| ビタミンE | 死亡率が高まる可能性があり |
| ビタミンB2 | 尿が黄色やオレンジに変色する |
| ビタミンB6 | 感覚神経障害、末梢感覚神経障害、骨の疼痛、精巣萎縮など |
| ビタミンC | 吐き気、下痢、腹痛、尿路結石(腎機能が低下している場合) |
| 亜鉛 | 胃障害、めまい、吐き気、銅欠乏や鉄欠乏に伴う貧血や免疫障害など |
| セレン | 爪の変形、脱毛、胃腸障害、下痢、末梢神経障害など※セレンは必要量と中毒量の差が小さいため特に注意が必要 |
| 大豆イソフラボン | 乳がん発症や再発のリスクを高める可能性も考えられる |
| カプサイシン | 流涙症、鼻液漏、排尿障害、胃食道逆流症など |
【出典:ビタミンA - 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:ビタミンD- 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:ビタミンE- 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:ビタミンB2- 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:ビタミンB6- 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:ビタミンC- 「 健康食品 」の安全性・有効性情報】
【出典:大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A|農林水産省】
【出典:カプサイシンに関する詳細情報|農林水産省】
水か白湯で飲む
薬に限らず、サプリメントでも飲むときは、水か白湯(ぬるま湯)が最適です。コーヒーや緑茶、牛乳、ジュースなどの飲料は、サプリメントの吸収を妨げたり、早めたり、中毒を引き起こしたりする可能性があります。
実際、お茶に含まれるカテキンには薬物を代謝する酵素を阻害する作用が確認されています。
牛乳やグレープフルーツジュースの摂取も相互作用があるため、避けましょう。
健康被害が出たりしないよう、サプリメントを飲む際は水か白湯がおすすめです。
【出典:各種茶飲料が薬物代謝酵素に及ぼす影響|科学技術振興機構(JST)】
【出典:食物と薬の相互作用(理論編)|e-ヘルスネット 厚生労働省】
長期的に飲み続ける
サプリメントは医薬品と異なります。また育毛自体も長期間の栄養摂取やケアを必要とします。そのため数ヶ月から数年は飲み続けることをおすすめします。
体調が悪くなったり、違和感を感じたりする場合は中断すべきですが、頻繁にサプリメントを変更するのは避けましょう。
他の薬との飲み合わせに注意する
サプリメントは食品や薬と同様、体内に作用する製品です。そのため、成分によっては薬と相互に影響しあい、悪影響を及ぼす可能性があります。
中には常用薬の効果が弱まったり、副作用が起こりやすくなったりする場合もあるため、サプリメントを使用する前に、かかりつけ医や薬局に相談しましょう。
また、サプリメントによく含まれている成分と飲み合わせに注意すべき薬を、以下の表にまとめました。いつも飲んでいる薬がある方やサプリメントを常服している方は、1度確認してみてください。
| 成分 | 影響する医薬品 | 影響 |
| ビタミンB6 | 抗てんかん薬(フェニトイン) | フェニトインの効力を約45%低下させる |
| 抗結核薬(イソニアジド) | イソニアジドの副作用である末梢神経障害を予防する | |
| 葉酸 | 抗腫瘍薬(フルオロウラシル、カペシタビン) | フルオロウラシルやカペシタビンの排泄を遅らせる |
| 抗腫瘍・免疫抑制・抗リウマチ薬(メトトレキサート) | メトトレキサートの副作用(下痢・口内炎・白血球減少など)を軽減する※ただし飲み過ぎるとメトトレキサートの効力が落ちるので注意が必要 | |
| 抗てんかん薬(フェニトイン・カルバマゼピン・バルプロ酸・フェノバルビタール・プリミドンなど) | 体内の葉酸量を低下させる | |
| チアジド系・ループ系利尿薬 | 葉酸の排泄が増加し、動脈硬化因子とされる血中ホモシステイン濃度が上昇する | |
| たんぱく質分解酵素(パンクレアチン)サルファ剤(サラゾスルファピリジン)コレステロール降下薬(コレスチラミン) | 葉酸の吸収を阻害する | |
| ビタミンC | 女性ホルモン(エチニルエストラジオール) | エチニルエストラジオールの効力が60%程度上昇する |
| 抗凝固剤(ワルファリン) | ワルファリンの作用を減弱させる | |
| ビタミンD | 抗結核薬(リファンピシン、イソニアジド) | ビタミンDの代謝を阻害し、活性型Dの血中濃度を低下させる可能性がある |
| ミネラル類 | テトラサイクリン系抗菌剤、キノロン系・ニューキノロン系抗菌剤など | 薬と結合し、吸収を阻害する |
【出典:食物と薬の相互作用(サプリメント編)|e-ヘルスネット 厚生労働省】
【出典:メトトレキサートを服用する患者さんへ|日本リウマチ学会】
まとめ
本記事では、育毛に必要に栄養素やサプリメントの飲み方に関して、解説しました。髪の健康を保つためには必要な栄養素はありますが、サプリメントだけでなく、バランスの良い食事や悪影響な食事を減らすことも重要です。